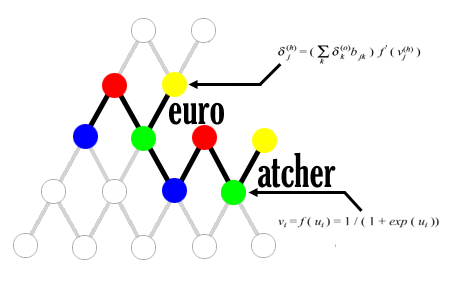与信限度額の設定方法をわかりやすく解説:超過した場合の対処法も紹介

はじめに
取引リスクを最小限に抑えるためには、与信限度額の設定が欠かせません。与信限度額を適切に管理すれば、過剰取引の抑制や不良債権の回避につながり、安定した取引関係の構築にも寄与します。
「ニューロウォッチャー」では現在、取引先財務情報のうち月商を基準に、平均回収日数と取引シェアを掛け合わせて算出する独自の「月商法」を採用しています。
2025年7月には、こうした月商法に加えて、6種類の新たな算出機能が「ニューロウォッチャー」に搭載されました。取引先の財務状況や自社のリスク許容度に応じて、より柔軟で戦略的な与信管理が実現可能になりました。
本コラムでは、与信限度額の基本的な考え方を整理しながら、ニューロウォッチャー独自の「月商法」を含む7種類の与信限度額算出方法の違いや活用ポイントについて、わかりやすく解説していきます。また、取引先との関係が変化した結果、売掛債権額や商談中の金額が与信限度額を超過した場合の適切な対処法についても触れていますので、取引の安全性を高める参考にしてください。
与信限度額とは? わかりやすく解説
与信限度額とは、企業が取引先に対して設定する「信用取引の上限額」を指します。上限額は、取引先が将来支払う予定額(売掛金)を制限し、債務不履行、回収不能のリスクを最小限に抑えるために設定します。
与信限度額の設定には、以下の3つの主な目的があります。
与信限度額設定の主な目的
| 回収リスクの軽減 | 取引金額の上限を設定し、回収リスクを最小限に抑制 |
|---|---|
| 資金繰りの安定化 | 未回収や不良債権リスクを回避し、自社のキャッシュフローを安定化 |
| 透明性の向上 | 明確な全社基準を設け、過剰取引の防止と取引継続判断の統一 |
与信限度額を設定し、その範囲で取引を徹底すれば、取引リスクの基準を見極めた客観的な経営判断が可能となります。
与信限度額設定の基準とは
与信限度額を設定する際には、「どの基準に基づいて上限を定めるか」が大きなポイントです。一般的には、「自社の財務基準」と「取引先の財務基準」の2つが代表的な判断軸 とされています。
「自社の財務基準」とは、自社の資産規模や損失許容範囲をもとに、万が一回収不能な事態が発生しても経営への影響を最小限に抑えられる水準で上限を決める方法です。この考え方は、複数の取引先に対して同一の基準で判断できるため、統一的な運用がしやすい利点があります。一方で、各取引先の実情を細かく反映しにくく、柔軟性に欠ける面も否めません。
これに対して、「取引先の財務基準」では、相手先の売上高や資産、債務などの財務内容をもとに、個別の支払能力に応じて与信限度額を算出します。実態に即した判断が可能となり、信用度の高い企業には拡大した枠を与えるなど、戦略的な調整がしやすい点が特徴です。ただし、正確な財務情報の収集や評価に一定の手間がかかる点には注意が必要です。
与信限度額設定の進め方
与信限度額を設定するための基本ステップは、以下の通りです。
- STEP1:自社能力の算定
- STEP2:取引先能力の算定
- STEP3:与信限度額の試算
- STEP4:与信限度額の調整
- STEP5:超過時のマニュアル作成
上記のステップを段階的に進めれば、取引リスクを最小限に抑えながら柔軟かつ効率的な与信管理が実現できます。
与信限度額設定の各ステップの詳細は、以下のコラム記事を参考にしてみてください。
与信限度額の具体的な設定方法
以下に紹介する7つの方式は、それぞれ異なる視点から与信限度額を導き出すアプローチです。取引先の特性に応じて、最適な手法を選択してください。
- 平均回収日数・取引シェアを用いた月商法
- 財務上限基準法
- 売上債権基準法
- 決済限度法
- 仕入債務基準法
- 月商一割法
- 内部留保基準法
それでは、各算出方法について詳しくみていきましょう。
平均回収日数・取引シェアを用いた月商法
ニューロウォッチャーでは、一般的な「月商法」をベースに、月間売上高に「平均回収日数」と「取引シェア」を掛け合わせる独自の算出方法を採用しています。単に売上だけに依存せず、信用度、取引先との親密度、代金回収サイトといった要素を考慮しており、実態に即した与信限度額を導き出せる設計となっています。
月商法は、売上情報の入手が比較的容易でシンプルな点から、社内の複数部門で共通の基準として活用しやすく、実務での判断基準としても親しまれています。
一方で、売り上げベースである以上、資金繰りや債務の状況といった経営の実態を反映しきれないケースもあるため、過信は禁物です。特に季節変動の激しい業種や、収益認識基準の変更によって売上の計上タイミングが変わった企業に対しては、与信枠が現実から乖離するリスクも考慮が必要です。
| 計算式 | 月間売上高 × 平均回収日数 ÷ 30 × 取引シェア *注1 |
|---|---|
| メリット |
|
| デメリット |
|
- 取引シェア:信用度に応じた取引関係の親密度(取引先の月商に占める自社の割合)のこと。
あらかじめ初期値が設定されているが、独自の設定やグループ別の設定も可能。
ニューロウォッチャーでは、従来よりこの方式を採用していますが、近年は収益認識に関する会計基準が変更され、売上の計上タイミングが従来と異なるケースも増えています。その結果、実態に比べて売上が少なく表示される企業も存在し、従来の月商法だけでは適切な与信判断が難しくなる場面も出てきました。
こうした背景を踏まえ、他の算出方法との併用も検討する必要があると考え、2025年7月に新たに6種類の算出機能を追加し、合計7種類の方式の中から、自社にとって最も適した方式を選択してご活用いただけるようになりました。
財務上限基準法
財務上限基準法は、自社の純資産をベースに与信限度額を算出する方法です。自社がどの程度の損失に耐えられるかの許容範囲を数値で可視化し、取引額の上限を設定します。
取引先の信用力を「重みづけ」として加味し、リスクの高低に応じて限度額に調整を加えます。例えば、信用格付が高い企業には重みづけを大きく設定し、より大きな与信枠を設けることが可能です。
| 計算式 | 純資産 × 一定割合 × 重みづけ (一般的に純資産10%がリスク許容範囲とされています) |
|---|---|
| メリット |
|
| デメリット |
|
財務上限基準法は、自社の財務健全性を反映した慎重な管理に適しています。必要に応じて、自社の総資産やキャッシュフローなどの他の指標と併用すれば、さらに精度の高い与信判断が実現します。
売上債権基準法
売上債権基準法は、自社の売上債権をもとに与信限度額を設定する方法です。実際の取引データに基づくため、理論だけに偏らず、現場の感覚に近いかたちで限度額を算出できます。
売上債権基準法では、売上債権の残高に一定の割合をかけ、さらに取引先の信用度に応じた「重みづけ」で調整を行います。取引先との関係性や取引実績を数値化できる点で、実務的な精度が高まることが特徴です。
| 計算式 | 売上債権額 × 一定割合 × 重みづけ |
|---|---|
| メリット |
|
| デメリット |
|
売上債権に基づく与信管理は、直近1~2ヶ月のキャッシュフローをもとに判断するため、短期的なリスクを把握しやすい一方で、長期的な視点では慎重な見直しが必要です。特に経済変動の影響を受けやすい取引先については、他の手法との併用も視野に入れてください。
決裁限度法
決裁限度法は、自社の決裁能力に基づいて与信限度額を設定する手法です。具体的には、社内の決裁権限やキャッシュフローの上限を基準に、無理のない範囲での与信管理を行います。
決裁限度法では、売掛金の発生に対して「自社が万が一の不払いにどれだけ対応できるか」という視点が重視されます。社内規定に沿った判断が可能で、急な取引拡大にも一定の柔軟性を持たせられます。
| 計算式 | 一定金額(自社の決裁上の上限額) × 重みづけ |
|---|---|
| メリット |
|
| デメリット |
|
決裁限度法は、社内での統制や予算管理と連動させやすい点が大きな特徴です。ただし、将来的な成長や安定性を評価する場合は、他の基準との併用が推奨されます。
仕入債務基準法
仕入債務基準法は、取引先の仕入債務を基準に与信限度額を算出する方法です。仕入債務とは、取引先が仕入先に対して未払いとなっている金額を指し、短期的な支払能力を評価する指標として活用されます。
仕入債務基準法では、仕入債務の総額に一定の割合を乗じ、さらに取引先の信用度に応じた重みづけを加えて限度額を調整します。仕入債務が過大になっている取引先は、すでに資金繰りに余裕がない可能性もあるため、慎重な見極めが必要です。
| 計算式 | 仕入債務 × 一定割合 × 重みづけ |
|---|---|
| メリット |
|
| デメリット |
|
取引先の仕入債務比率が高い場合、自社に与える影響が大きくなる可能性があります。こうした状況では、資金繰りや債務構成を多角的に分析し、破綻リスクを見落とさないように細心の注意が求められます。
月商一割法
月商一割法は、取引先の月間売上高を基準に、与信限度額をおおむね10%以下に抑えるというシンプルな手法です。売上高を信用の根拠とし、「売上の一定範囲であれば支払可能」とみなして与信枠を決定します。
月商一割法は、計算が非常に容易であるため、多くの企業で基本指標として採用されています。財務情報を詳しく開示していない取引先であっても、企業情報として売上高だけは把握できるケースが多いため、導入のハードルも低めです。
| 計算式 | 月間売上高 × 10%以下 |
|---|---|
| メリット |
|
| デメリット |
|
業種によって売上の構造やタイミングが異なるため、単純に売上の10%と決めつけるのではなく、商流や契約条件などもあわせて評価したうえで柔軟に調整する姿勢が求められます。
内部留保基準法
内部留保基準法は、取引先の自己資本を基準に、与信限度額を設定する方法です。
企業が保有する自己資本は、財務的な安定性を示す指標の一つとされています。内部留保基準法では、内部留保の規模が大きいほど、経営体力があるとみなし、高めの与信枠を設定しやすくなります。自己資本は資本構成の健全性を評価するうえでも有効な指標です。
| 計算方法 | 取引先自己資本 × 一定割合 × 重みづけ |
|---|---|
| メリット |
|
| デメリット |
|
内部留保基準法は、中長期の視点で取引先の信頼性を評価する際に有効です。ただし、現金や流動資産といった即時の支払能力とは性質が異なるため、短期的な判断には別指標との併用がおすすめです。
2025年7月のアップデートによる実務面でのメリット
ここまで、異なる視点から与信限度額を導き出す7つの設定方法をご紹介しました。
AGSの与信管理サービス「ニューロウォッチャー」では、取引先の規模、信用度、取引関係の親密度、代金回収サイトにより算出される、独自の月商法を採用していましたが、状況に応じた柔軟な与信管理を実現するため、「財務上限基準法」などの6種類の与信限度額算出機能を、2025年7月に新たにリリースしました。
このアップデートにより、以下のような実務面でのメリットが期待いただけます。
| メリット | |
|---|---|
| 自社基準をもとに判断できる | 財務上限基準法、売上債権基準法、決裁限度法では、自社の財務情報を基準値として保存・活用できるため、限度額の一貫性と管理効率が高まります。 |
| 財務情報の再活用が可能 | 仕入債務基準法、月商一割法、内部留保基準法では、ニューロウォッチャーにて財務情報を取得すれば、計算に必要な情報は自動で反映されます。また、財務情報が公開されていない企業の場合などは、数値を手入力することも可能です。 |
与信限度額を超過した場合の対処法
万が一、取引先との取引が与信限度額を超過する状況が発生した場合には、新たな取引を停止したり、事前に現金や保証金を要求するなどの状況に応じた対処が必要です。
ここでは、以下のような代表的なケースとその対処方法を解説します。
- 取引先が好調で取引規模が拡大した場合
- 取引先の信用状態に懸念が発生した場合
- 与信限度額は定期的に見直すことが重要
各事例を参考に、与信限度額の運用方法を再チェックしてみましょう。
1. 取引先が好調で取引規模が拡大した場合
取引先の業績が好調で取引量が急増し、与信限度額を超過する場合があります。その際は、以下のポイントを確認してみてください。
| 与信の再審査 | 最新の企業情報や格付情報の入手、および過去の取引実績や支払履歴(支払遅延の有無)などを確認 |
|---|---|
| 与信限度額の増加 | 問題がなければ、リスクを慎重に評価しながら与信限度額を引き上げる |
最新の財務情報を基に再度与信審査を実施し、限度額の見直しを検討しましょう。
2. 取引先の信用状態に懸念がある場合
信用状態が悪化している取引先との取引が、与信限度額を超過するリスクがある場合は、迅速かつ適切な対策を講じ、売掛債権を減らす方向で進める必要があります。
| 与信限度額の減少 | 取引先に発生したリスクを評価し、与信限度額を決める (状況によっては前払いを条件にするなど、取引条件を厳しくする) |
|---|---|
| 追加保証の要請 | 取引先に担保や第三者保証を求め安全性を高める |
状況に応じて定期的に取引先の信用情報を更新し、変化を早期に察知する対応が必要です。
3. 与信限度額は定期的に見直すことが重要
与信限度額は、取引先の信用状態や経営状況の変化に対応するため、定期的に見直すことが重要です。
最低でも年1回、取引先の決算期を基準に情報を収集し、限度額を再設定しましょう。
例えば、3月決算の企業であれば、7月頃に情報収集を開始し、10月から11月にかけて新たな限度額を決定するのが一般的です。
また、重要な取引先や信用状態に懸念のある企業については、通常より頻度を上げ、半年や四半期ごとに見直す対応が求められます。これにより、リスクを早期に察知し、適切な対策が可能となります。
さらに、社内で見直しルールを明確にし、対応期限を定めることで、管理の効率化が図れます。定期的な見直しを行うことで、リスクを軽減しつつ、取引先との信頼関係を維持しましょう。
まとめ|与信限度額設定は、取引リスク最小化のための重要なプロセス
与信限度額の設定は、企業の取引リスクを最小限に抑えるための重要なプロセスです。
本コラムでは、ニューロウォッチャーに実装している7種類の与信限度額算出方法について紹介しました。
取引先の信用力や取引履歴などの多角的なデータを基に厳格な設定を行うことが重要であり、限度額を超過した場合には迅速かつ適切な対応が求められます。
AGSの「ニューロウォッチャー」は、取引先の信用格付や与信限度額の算出を効率的に行うサービスです。
2025年7月に与信限度額の算出機能が大幅にアップデートされ、従来の、取引先の規模・信用度(安全性)・親密度・回収サイトを基準にした、信頼性の高い与信限度額算出機能に加え、6種類(自社財務を基準に3種類、取引先財務を基準に3種類)の与信限度額算出機能が追加され、合計7種類の方式を自由に利用できるようになり、自社に最も適した算出方式を選択してご活用いただけるサービスとなっております。
これを機に、自社の与信管理体制をさらに強化してはいかがでしょうか。